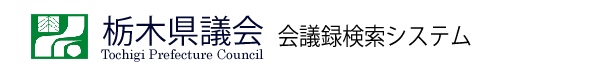現在位置 :トップページ › 請願・陳情の詳細情報 › ・ス・ス・スハ支・ス・ス・スw・スZ・スフ環具ソス・ス・ス・ス・ス・スA・ス・スh・スノ具ソス・ス・ス・ス・スp・ス・ス・ス・ス・ス髏ァ・スx・スン計・ス・ス・ス・ス・ス゚ゑソスツ情書
請願・陳情の詳細情報表示
第24号(令和07年) 特別支援学校の環境整備、寄宿舎教育を継承する制度設計を求める陳情書
| 受理番号 | 第24号 (令和07年) |
受理年月日 | 令和7年2月17日 |
|---|---|---|---|
| 付託委員会 | 文教警察委員会 | 委員会付託年月日 | 令和7年2月26日 |
| 議決結果 | 不採択 | 議決年月日 | 令和7年3月24日 |
| 紹介議員 | |||
| 第24号(令和07年) 特別支援学校の環境整備、寄宿舎教育を継承する制度設計を求める陳情書 一 陳情の趣旨 令和6(2024)年8月に示す「特別支援教育の充実に向けた方針」に基づき、特別支援学校寄宿舎及び寄宿舎指導員の在り方を踏まえた特別支援学校の環境整備、特別支援教育を担う教師の専門性向上の考えを示す。 二 陳情の理由 栃木県教育委員会(以下、県教委)は、令和3(2021)年に那須特別支援学校並びに栃木特別支援学校寄宿舎の閉舎を令和5(2023)年3月末までと発表をしたが、寄宿舎存続の声が挙がったことを受け、特別支援教育の在り方検討会を設け、「寄宿舎は発展的解消が望ましい」の報告を踏まえ、令和6(2024)年8月に「特別支援教育の充実に向けた方針」(以下、方針)を示しました。 これまで、特別支援学校(知的障害)の寄宿舎教育に関する陳情書を5度の提出にて訴えてきました。特別支援学校においては、寄宿舎設置や寄宿舎指導員配置について法的な定めがあります。社会的にも特別支援教育への認識や理解が高まり、法改正なども行われ、インクルーシブ教育の理念を踏まえた特別支援教育をめぐる状況は変化しています。そしてこの動向は、県教委も方針の基本的考え方に謳っているところです。 県教委は「寄宿舎の発展的解消が望ましい」という内容の報告から、寄宿舎教育が担ってきた教育の在り方は、寄宿舎を利用できる一部の児童生徒に限ることなく、特別支援学校に通う全ての児童生徒にその教育を図ることを示したものと考えられます。しかし、寄宿舎教育が、寄宿舎を利用できる一部の児童生徒に限られた教育ではなく、寄宿舎や寄宿舎指導員の在り方を整理することで、自立と社会参加を目指した生活力を高めるためのより良い支援・指導の方向性ができるものと考えられます。寄宿舎は学校教育法に則った、児童生徒の安心・安全が保障された教育現場であり、知的障害の子どもの自立を促し、自己決定を導く重要な教育機会のひとつと考えられます。寄宿舎教育は寄宿舎という教育施設があることにより、その時代のニーズに沿った寄宿舎教育がなされてきました。学校教職員と同様に、寄宿舎指導員は子どもの教育に指導的立場から児童生徒に向き合って、担当する児童生徒との信頼を築き、生活指導・健康管理・安全管理・業務分掌の運営、そして研究・研修に励み、児童生徒一人一人の課題解決に向けた取り組みを意図的・計画的に行うことが求められているところです。 また、県教委は、栃木県教育振興基本計画2025 基本施策3「特別支援教育の充実」における主な取組として、「教員の理解促進と実践的な指導力の向上」を示しています。今回の寄宿舎閉舎によって、実践的指導の場が失われたと感じます。県議会でも、寄宿舎を併設する学校と無い学校では教育の公平性がないとありますが、特別支援学校教育の充実という観点からは、寄宿舎教育が果たしてきた機能を検証し、その教育をすべての特別支援学校に継承し実践することで、特別支援教育の充実・発展に繋がったであろうと残念に思います。県議会には、県教委が特別支援教育の充実に向かうため、寄宿舎指導員が果たしてきた教育的意義を再検証し、寄宿舎教育の生活教育の実践をすべての特別支援学校に導入・継承できるシステムづくり・制度設計を強く要望いたします。 |
|||