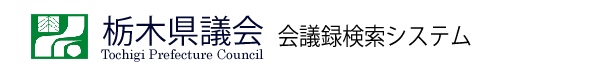現在位置 :トップページ › 請願・陳情の詳細情報 › 請願・陳情の詳細情報
請願・陳情の詳細情報表示
第20号(令和06年) 学校教育法の視点からの寄宿舎教育審議会と特別支援教育の充実に向けた方針を実現するための特別支援教育推進協議会の設置並びに審議会・協議会の検証を行う第三者機関設置を求める陳情書
| 受理番号 | 第20号 (令和06年) |
受理年月日 | 令和6年12月9日 |
|---|---|---|---|
| 付託委員会 | 文教警察委員会 | 委員会付託年月日 | |
| 議決結果 | 不採択 | 議決年月日 | 令和6年12月26日 |
| 紹介議員 | |||
| 第20号(令和06年) 学校教育法の視点からの寄宿舎教育審議会と特別支援教育の充実に向けた方針を実現するための特別支援教育推進協議会の設置並びに審議会・協議会の検証を行う第三者機関設置を求める陳情書 一 陳情の趣旨 1.栃木県教育委員会(以下、県教委)が8月に示した「特別支援教育の充実に向けた方針」は、寄宿舎の存廃問題より発展した課題であることが念頭に置かれなくてはなりません。寄宿舎教育は学校教育法に基づいた教育の一つである以上、寄宿舎教育の審議会の設置を求めます。 2.寄宿舎の存廃問題から発展した「特別支援教育の充実に向けた方針」が、県教委から公表されました。「共生社会の実現に向けた視点」として3つの柱を掲げ、具体的取り組みとして大分類2項目、中分類5項目、小分類16項目を掲げています。1 6項目ごとを丁寧に考える特別支援教育推進協議会の設置を求めます。 3.趣旨1並びに趣旨2においての審議会・協議会は、障害者権利条約に基づき当事者を含め関係者や有識者を交えた人選とし、その審議会・協議会が共生社会の実現に向けた視点に基づいて取り組みがされているか検証を行う第三者機関を設けることを求めます。 二 陳情の理由 1.県教委は、令和6年8月19日に開催した臨時会にて正式に那須特別支援学校並びに栃木特別支援学校に設置する寄宿舎の閉舎を決定しました。また、9月県議会においては、教育補正予算に寄宿舎解体費用も含め可決され、解体入札が決まりました。特別支援教育の在り方検討会からの報告にあった「発展的解消」から、寄宿舎教育の効果や有効性を評価した上で(知的特支学校)寄宿舎を閉舎した後、寄宿舎指導員を含めたワーキンググループを設けての寄宿舎教育の継承を図るとありますが、具体的な取り組みに進む以前の課題として寄宿舎が存在しない中での寄宿舎教育は当然ながら従前の機能は果たせませんし、寄宿舎指導員も従前の立場と異なった教職員としてどのような職務を求めるのか、理解いたしかねます。学校教育法に基づいた寄宿舎において、寄宿舎指導員は個々の障害に応じた生活指導で丁寧に自立や本人の意思決定支援など、卒業後の社会生活に向けた自立支援のための教育を担ってきました。そこには、寮母から寄宿舎指導員となった当初からの教育理念がブレずに取り組まれてきたことが、そこに関わった児童生徒の成長につながったとも言えます。もちろん、寄宿舎指導員だけの効果とは限らず、学校教職員とくに担任との相談をしながらの取り組みがあったからこそより効果が育まれたと実感しております。また、その教育の在り方を県教委がしっかりと守ってきたという歴史が、県教委が認める寄宿舎教育の効果や有効性の評価となり、同時に当事者や保護者らのニーズに沿った寄宿舎教育の有効性が大きな評価を受けていると言えます。これまでの成果を寄宿舎閉舎後の特別支援教育の中にどのように継承していくべきかは、大きな課題となるはずです。そこで、寄宿舎教育を学校教育法に基づいた視点から寄宿舎教育の意義を検証するための寄宿舎教育審議会の設置を求めるものです。 2.「特別支援教育の充実に向けた方針」は、多岐に広がる支援教育の課題の取り組みから「共生社会の実現に向けた視点」を掲げ、インクルーシプ教育・共生社会へつながる教育を目指すものと感じます。この取り組みは、栃木県内すべての特別支援学校保護者にアンケートを実施し、回答者の9割近い保護者から総意での実施に取り組みをはじめるものであると表明をしています。保護者の期待を大きく受け、すべての項目の実施に向けての取り組みは安易な取り組みではないと同時に大きな責務だと感じます。そこで1 6項目すべての実現に向け、項目に沿った当事者や専門家など必要に応じた人選で協議を進めることが必要であり、そのための特別支援教育推進協議会を設置することを切望します。丁寧な協議を行うことで、具体的な取り組みを表面化し実現化をすることで特別支援学校が支援教育のセンター的役割機能をさらに充実をさせ、インクルーシブ教育や共生社会の実現に近づくものと考えます。 3.今回の寄宿舎閉舎の決定や特別支援教育の充実に向けた方針に対する具体的取り組み1 6項目の策定に関しては、寄宿舎利用の保護者との面談やすべての支援学校保護者へのアンケートなど、県教委が直接対応をすることは過去になかった姿勢です。そこで、今回の陳情書で求めました協議会の在り方については、障害者権利条約にあるように緊密な協議を行っていただけると非常に期待ができるところです。寄宿舎教育の在り方、特別支援教育の充実に向けた方針1 6項目について、個別の協議が必要となるところです。幅広い意見を受け議論する審議会並びに協議会とその取り組みが機能を果たしているか検証のための第三者機関を設けることで、アンケートに答えた保護者の期待と県民向け意見交換会での県教委が示した内容への責任を果たすべきと考えます。また、これまで県議会から県教委に提言をされた丁寧な説明責任に直結するところです。議員各位におかれましては本陳情を真摯に受け止め民意に沿ったご判断を求めます。 |
|||