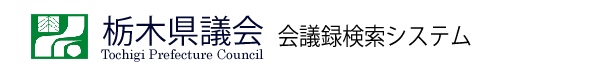尰嵼埵抲 丗僩僢僾儁乕僕 › 惪婅丒捖忣偺徻嵶忣曬 › 丒絳丒絳丒疥寶锟捷偵傦拷丒窖抧丒絁丒絹E絹E絹E絹E铰怽丒絹E絹E教嬶拷丒铰庯拷丒絹E絹E絹E教捖忥拷
惪婅丒捖忣偺徻嵶忣曬昞帵
戞7崋(椷榓06擭)丂梴寋応寶愝偵傛傞椦抧奐敪嫋壜怽惪偺嫋壜庢徚偟偺捖忣
| 庴棟斣崋 | 戞7崋 (椷榓06擭) |
庴棟擭寧擔 | 椷榓6擭4寧12擔 |
|---|---|---|---|
| 晅戸埾堳夛 | 擾椦娐嫬埾堳夛 | 埾堳夛晅戸擭寧擔 | 椷榓6擭6寧4擔 |
| 媍寛寢壥 | 晄嵦戰 | 媍寛擭寧擔 | 椷榓6擭6寧14擔 |
| 徯夘媍堳 | |||
| 戞7崋(椷榓06擭) 梴寋応寶愝偵傛傞椦抧奐敪嫋壜怽惪偺嫋壜庢徚偟偺捖忣 1 捖忣偺庯巪 (1)丂仜仜仜偺仜仜仜偺愝抲偵偮偄偰丄偦偺椦抧奐敪嫋壜怽惪偺嫋壜傪庢傝徚偟偰捀偒偨偄 嘆 仜仜仜偼導偺帠慜嫤媍偵娭楢偟偰懡悢偺嫊婾偺愢柧傪峴偄丄偦偺愝抲嫋壜傪摼偨 丒椷榓5擭搙乽仜仜仜偺愝抲乿偵娭偡傞帠慜嫤媍嵟廔曬崘彂偺拞偵婰嵹偝傟偨媍帠榐拞偵帺帯夛挿丄仜仜仜偺敪尵偲偟偰婰嵹偝傟偰偄傞撪梕偵暋悢偺嫊婾婰嵹偑偁傞丅彮側偔偲傕帺帯夛挿偑摉奩仜仜仜偺愝抲偵巀摨偟偨帠幚偼側偔丄傑偨嬤椬偱斀懳塣摦偑側偄巪偺婰弎偼丄斀懳棫偰娕斅偑暋悢愝抲偝傟丄帺帯夛峔惉堳偺杦偳(屗悢偱栺70%) 偑斀懳彁柤傪偍偙側偭偰偄傞帠幚偲偼堎側傞丅 丒椷榓5擭9寧28擔偵峴傢傟偨撊栘導媍夛擾椦娐嫬埾堳夛偵偮偄偰丄仜仜仜傛傝廧柉偵懳偟偰帺敪揑側愢柧妶摦偑峴傢傟偨帠幚傕側偔丄巗偼廧柉偲偺懪崌偣偵枅夞嶲壛偟偰偄側偄丅偙偺揰傕擾椦娐嫬埾堳夛(徏堜埾堳)偵懳偡傞仜仜仜偺嫊婾愢柧偑峴傢傟偨帠幚偲尒橍偣傞丅 丒擾椦惍旛壽丄壨愳壽丄仜仜仜搚栘帠柋強偺偄偢傟傕偑敪尵偟偰偄側偄撪梕傪漵憿偟丄偁偨偐傕偙傟傜偺晹栧偐傜偺巜摫傪棟桼偵丄朄椷忋塉悈攔悈偼帺慠曻棳曽幃傪尨懃偲偡傞偲偙傠怹摟曽幃偵椺奜曄峏偟偰偄傞丅 丒忣曬岞奐惪媮張暘偵懳偡傞怰嵏惪媮偺曎柧彂(抺怳戞1026崋)偵偰丄擾応偵懳偡傞廧柉傊偺愢柧傪仜仜仜偼偙傟傑偱傕偢偭偲愢柧偟懕偗偰偒偰偄傞偲偺嫊婾曬崘傪峴偭偰偄傞丅 嘇 仜仜仜偑愝抲嫋壜傪摼偨仜仜仜偼丄抧尦廧柉偺奐敪摨堄偑晄廫暘側傑傑丄偦偺愝抲嫋壜傪摼偨傕偺偱偁傞丅 丒椦抧奐敪怽惪偺怰媍婎弨堦斒帠崁偺奐敪偵偍偗傞乽憡摉悢偺摨堄乿偵偮偄偰丄帺帯夛堳偺70%埲忋偑寶愝偵斀懳偟偰偍傝丄乽偦偺懠偺 幰乿偵偮偄偰偺摨堄偑晄廫暘偱偁傞偙偲傪帵偟偰偄傞丅 嘊仜仜仜偑愝抲嫋壜傪摼偨仜仜仜偼丄怷椦朄偺悈奞偺杊巭偵栤戣偑側偄柧妋側崻嫆傪帵偝側偄傑傑晄摉偵丄偦偺愝抲嫋壜傪摼偨丅 丒塉悈攔悈偺怹摟曽幃偼丄怷椦朄偺悈奞偺杊巭偺娤揰偺椺奜曽幃偱偁傝丄夁嫀偵悈奞偺幚椺偺偁傞椬愙偡傞掅抧擾抧傊偺悈奞儕僗僋偑偁傞丅 俀 捖忣偺棟桼 (1)丂棟桼 椷榓5擭搙乽仜仜仜偺愝抲乿偵娭偡傞帠慜嫤媍嵟廔曬崘彂偱抧堟怳嫽壽巜摫帠崁偺夞摎偲偟偰揧晅偝傟偨乽愢柧夛媦傃幚巤忬嫷乿偺媍帠榐偺拞偱丄帺帯夛挿丄仜仜仜偺敪尵奣梫偵暋悢偺嫊婾婰嵹丒嫊婾曬崘偑偁偭偨偙偲偼丄婛偵椷榓5擭3寧18擔偵仜仜仜傛傝仜仜仜巗仜仜仜壽偵捠曬偑偁偭偨捠傝偱偁傞丅 (揧晅帒椏嘆嶲徠)偙傟偼丄導偲帠嬈幰偺2幰偵傛傞帠慜嫤媍偲偄偆廧柉晄嵼偺応(僠僃僢僋婡擻側偟)偱峴傢傟偨嫊婾曬崘偱偁傝丄媍帠榐拞 偺敪尵幰偺怣梡傪婞懝偡傞埆幙側晄惓峴堊偱偁傞丅 偝傜偵丄偙偺帠慜嫤媍嵟廔曬崘彂偼丄椷榓5擭9寧28擔偵峴傢傟偨撊栘導媍夛擾椦娐嫬埾堳夛偵偍偄偰変乆偑採弌偟偨庴棟斣崋2斣偺捖忣偺怰媍偺朻摢偱嫤媍忬嫷偲偟偰幏峴晹傛傝愢柧偝傟偰偍傝丄帠嬈幰偐傜偼愊嬌揑側廧柉愢柧偑峴傢傟偰偄偰抧尦偲偼椙岲側娭學偱偁傞偲偺埾堳偺岆敾抐傪桿敪偟捖忣偼寢嬊晄嵦戰偲側偭偨丅(揧晅帒椏嘇嶲徠)丅帠嬈幰懁偑堄恾揑偵榗嬋偟偨帠幚偲堎側傞忣曬傪梡偄偨峴惌傊偺愢柧偼丄曃偭偨桿摫偱偁傝丄柉堄傪擖傟傞媍榑偺応傪榗傔偨岞惓側庤懕偒偵懳偡傞朻摾偱偁傞丅 怷椦朄偺悈奞杊巭偵娭偡傞帠崁偲偟偰乽峖悈挷惍偺曽幃偼丄尨懃偲偟偰帺慠曻棳曽幃偱偁傞偙偲乿偲偝傟偰偄傞丅偟偐偟側偑傜丄偙傟傪柍帇偟偰乽導偺巜摫傕偁傝丄仜仜仜愳偺壨彴偺曽偑崅偄偨傔帺慠曻棳晄壜乿偲偄偆嫊婾偲埨堈側棟桼偱椺奜曽幃偱偁傞怹摟曽幃傪嵦梡偟偰偄傞丅導擾椦惍旛壽丄壨愳壽丄仜仜仜搚栘帠柋強丄偄偢傟傕怹摟曽幃傪巜摫偟偨偙偲偼側偄偲妋擣嵪傒偱偁傝丄乽導偺巜摫傕偁傝乿偲偄偆偺偼嫊婾曬崘偱偁傞偙偲偼婛偵敾柧偟偰偄傞丅傑偨丄壓棳曽岦偵桿摫偡傟偽廃曈偼擾抧偱幷傞傕偺偼側偔壨愳偺曽偑掅偔側傝丄仜仜仜愳傊偺帺慠曻棳偼媄弍揑偵壜擻偱偁傞丅(揧晅帒椏嘊嶲徠) 巹偨偪偼仜仜仜偺婛懚梴寋応偵偮偄偰丄塩嬈奐巒偐傜栺仜仜仜擭偵傕側傞偑丄戝婯柾帠嬈幰偵媮傔傜傟傞乽娔帇揱愼昦偺敪惗偵旛偊偨懳墳寁夋乿偵娭偡傞廃曈廧柉傊偺棟夝偺忴惉偲偟偰偺愢柧夛摍偑堦搙傕側偄偙偲偐傜丄仜仜仜壠抺曐寬塹惗強偵忋婰懳墳寁夋偺奐帵惪媮傪峴偭偨丅偙傟偵懳偡傞曎柧彂(揧晅帒椏嘋嶲徠)偺拞偱丄乽側偍丄摉奩擾応偐傜偼丄廧柉愢柧偼偙傟傑偱傕峴偭偰偄傞偲偺夞摎傪摼偰偄傞偲偙傠偱偁傞丅乿偲偺庍柧傪摼偰偍傝丄曐寬強偵懳偟偰傕仜仜仜偼嫊婾曬崘傪峴偭偨偲悇嶡偝傟傞丅偪側傒偵丄奐帵偝傟偨懳墳寁夋彂偺嶌惉幰偼仜仜仜壠抺曐寬塹惗強偱偁傝丄摉奩擾応偱偼側偄丅 椦抧奐敪嫋壜怽惪惂搙偵庤堷彂偵傛傟偽丄怰嵏婎弨偺堦斒帠崁偱乽憡摉悢偺摨堄乿傪摼傞偙偲偲側偭偰偄傞丅偙偺乽憡摉悢偺摨堄乿偲偼奐敪梡抧丄椬愙抧偺摨堄偺傒側傜偢丄乽偦偺懠偺幰偵偮偄偰傕摨堄傪摼傞偙偲偑偱偒傞偲擣傔傜傟傞応崌乿偲婯掕偟偰偄傞丅偲偙傠偑丄仜仜仜廧柉偺栺70%偼偙偺偨傃偺奐敪寁夋偵斀懳彁柤傪峴偄丄斀懳偺堄傪帵偟偰偄傞丅(揧晅帒椏嘍嶲徠) 悈奞杊巭偺娤揰偱尨懃偲偟偰偄傞帺慠曻棳傪峴傢偢丄怹摟曽幃偲偄偆椺奜曽幃傪嵦梡偡傞偙偲偺棟桼偲娫戣偑側偄偙偲偺柧妋側崻嫆偑側偄(棳検寁嶼偵偰埨慡妋擣偡傞傕偦傟偼怹摟傑偱偺榖偱丄偦偺悈偑壓棳晹偱桸偒偁偑偭偰悈奞傪傕偨傜偝側偄偐傑偱昡壙偝傟偰偄側偄丄偮傑傝丄悈奞偺杊巭傪妋擣偡傞傕偺偲偼側偭偰偄側偄)丅偙偺傑傑怹摟曽幃偱寶愝偝傟傞偺偼怷椦朄偺朄椷堘斀偱偁傞丅(揧晅帒椏嘐嶲徠) ( 2 )栚揑 丒晄惓偵摼偨嫋壜偼朄偺壓偵偦偺嫋壜偼庢傝徚偝傟丄偦偺忋偱丄嵞搙怰嵏婎弨偵徠傜偟崌傢偣偨嵞怰嵏傪峴偆偙偲丅 丒帠嬈幰偼丄抧尦抧堟偵椙偄偙偲傕埆偄偙偲傕塀偡偙偲側偔岞昞偟丄怣棅偺夞暅偵搘傔傞偙偲丅(偙傟偑偱偒側偄偲丄戝婯柾壠抺強桳幰偲偟偰壠抺揱愼昦梊杊朄偺壓偱偦偺愑柋傪壥偨偣側偄丅)偦偺忋偱嬯忣丒梫朷偵恀潟偵墳懳偡傞偙偲丅 丒塉悈攔悈張棟偼怷椦朄偺悈奞杊巭偵學傞婎杮揑偐偮廳梫側婎弨偱偁傞丅尨懃偵増偭偰塉悈攔悈張棟偼帺慠曻棳偲偡傋偒偱偁傝丄廫暘偵専摙偟偮偔偡偙偲丅 丒偳偆偟偰傕怹摟抮偲偣偞傞傪摼側偄偺偱偁傟偽丄帺慠曻棳偑偱偒側偄棟桼傪柧妋偵帵偟丄悈奞偺栤戣偑婲偒側偄偙偲傪柧妋偵帵偟偨偆偊偱丄枩偑堦悈奞偑敪惗偟偨応崌偺愑擟丒曗彏偺嵼傝曽傪嫤掕彂偵柧婰偟偰娭學幰偱崌堄偡傞偙偲丅 丒導媍夛偺媍榑傪榗傔丄媍夛傪朻摾偟偨偲傕偲傟傞桼乆偟偒帠懺偱偁傝丄峴惌偱偼夝寛偑朷傔側偄偲峫偊導媍夛偵捖忣偡傞傕偺偱偡丅導偼岆偭偨怰嵏姷椺傪尒捈偟丄岞惓偵懳張偡傞偙偲丅 俁 揧晅帒椏 嘆丂帠慜嫤媍曬崘彂撪媍帠榐偺嫊婾婰嵹丒嫊婾曬崘偺徹尵 嘇丂椷榓俆擭俋寧擾椦娐嫬埾堳夛媍帠榐(敳悎) 嘊丂導壨愳壽丄仜仜仜搚栘帠柋強偲偺懪偪崌傢偣媍帠榐(敳悎) 嘋丂怷椦朄偵婎偯偔椦抧奐敪嫋壜怽惪偺庤堷偒(敳悎) 嘍丂彁柤曤(仜仜仜抧嬫) 嘐丂悈奞儕僗僋偵偮偄偰 仸揧晅帒椏偼帠柋嬊曐娗 |
|||