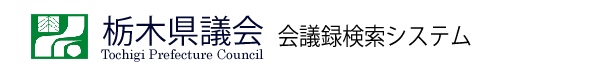現在位置 :トップページ › 請願・陳情の詳細情報 › ・ス・ス・スノ対ゑソス・スト「・ス・ス・ス・ス・ス}・ス{・ス闢厄ソスフ鯉ソス・スz・スフ鯉ソス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス゚ゑソスv・スモ鯉ソス・ス・ス・スフ托ソス・ス・ス・ス・ス・ス゚ゑソスツ擾ソス
請願・陳情の詳細情報表示
第93号(平成19年) 国に対して「児童扶養手当の減額の見直しを求める」意見書採択を求める陳情
| 受理番号 | 第93号 (平成19年) |
受理年月日 | 平成19年2月19日 |
|---|---|---|---|
| 付託委員会 | 厚生環境委員会 | 委員会付託年月日 | 平成19年3月1日 |
| 議決結果 | 不採択 | 議決年月日 | 平成19年3月9日 |
| 紹介議員 | |||
| 第93号(平成19年) 国に対して「児童扶養手当の減額の見直しを求める」意見書採択を求める陳情 【陳情趣旨】 2002年の母子寡婦福祉法の改定により、児童扶養手当の5年間支給後あるいは7年間経遇後の手当の減額が、2008年度からおこなわれることになっています。すでに、02年の改定で母子家庭の半数が手当を減額され、2006年には国庫負担率が4分の3から3分の1に削減、手当支給の地域格差が心配される中、さらなる手当の減額は、今でも苦しい母子の暮らしを直撃します。 2003年からの、母子家庭等自立支援対策大綱にのっとった、各自治体の自立支援事業は、いまだに取り組まれていない自治体も多く、職業紹介されても非正規の仕事、住宅事情は改善されず、安定した暮らしを営む助けにはなっていないのが現状です。 母子家庭の母親の就労は83%(内非正規49%)、平均収入は子どものいる世帯全体の平均年収の30%強です。収入増のための長時間労働や複合就労により、親子で過ごす時間がなくなり、子どもを安心して育てられる状況ではありません。 生活保護基準以下の収入で暮らす母子家庭が多いなか、児童扶養手当は、仕事と暮らしを両立させて子どもを育てていくうえで大きな支えになっています。 自立支援対策の実効性が上がっていると言えない状況のなか、母子家庭がさらなる苦境に陥ることのないよう、国に対して次の点で意見書をあげてくだきるようつよく求めます。 【陳情事項】 1.児童扶養手当の5年間支給後あるいは7年経過後の減額はしないこと。 2.02年の付帯決議を守り、国の責任で実施の促進をはかること。 |
|||