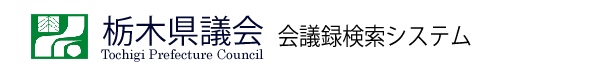現在位置 :トップページ › 意見書・決議 議決結果一覧 › ・ス}・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・スQ・ス・スh・ス~・ス・ス・ス驍ス・ス゚の法・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス゚ゑソスモ鯉ソス・ス・ス
意見書・決議の詳細情報
第1237号 急増する金属盗被害を防止するための法整備を求める意見書
| 番号 | 第1237号 | 議決年月日 | 令和6年6月14日 |
|---|---|---|---|
| 議決結果 | 可決 | ||
| 議第 2 号 急増する金属盗被害を防止するための法整備を求める意見書 近年、資材価格の高騰に伴い金属類の取引価格が上昇していることを背景に、太陽光発電所のケーブル、道路側溝のグレーチング、橋名板などの金属類について、売却を目的とした窃盗被害が全国各地で相次いでいる。 警察庁によると、全国で昨年1年間に確認された金属類の盗難件数は、前年より5,908件増の1万6,276件と首都圏を中心に被害が急増しているとのことであり、本県では、金属盗の認知件数は令和2年の376件だったものが令和5年には1,464件と4倍近くに跳ね上がり、全国ワースト3位の高い水準となっている。 被害急増の要因としては、山中の太陽光発電所など監視の目が届きにくい場所が狙われるため、通常の防犯対策だけでは被害を食い止めることが困難な現状にあることや、金属類の市場価格の高騰に伴って取扱業者が増え、盗品を売却しやすい環境があることが指摘されており、過去の検挙事例からは、外国人グループが複数の県で盗みを重ねて買い取り業者に売却し、不法滞在外国人の収入源になっているとも指摘されているなど、金属盗の急増は治安上の大きな課題になっている。 このような中、被害の多い自治体では、条例の制定・改正により、取引時の氏名や住所の確認、不正品の疑いがある場合の警察への申告、取引記録の保存などを義務付け、盗品の換金を防ぐことで犯罪を抑止しようという動きも出てきているが、条例等により自治体独自に規制を行ったとしても、規制のない自治体に盗品が持ち出され売却されることも想定され、抜本的な解決にはつながらないことから、不法に入手した金属を売却し利益を得ることを防ぐ、法的な仕組みが必要である。 よって、国においては、国民の財産を守るため、急増する金属盗被害を防止するための法整備を早急に行うよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和6年6月14日 栃木県議会議長 日向野 義 幸 内 閣 総 理 大 臣 法 務 大 臣 宛て 国家公安委員会委 員 長 衆 参 両 院 議 長 |
|||